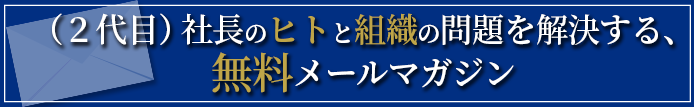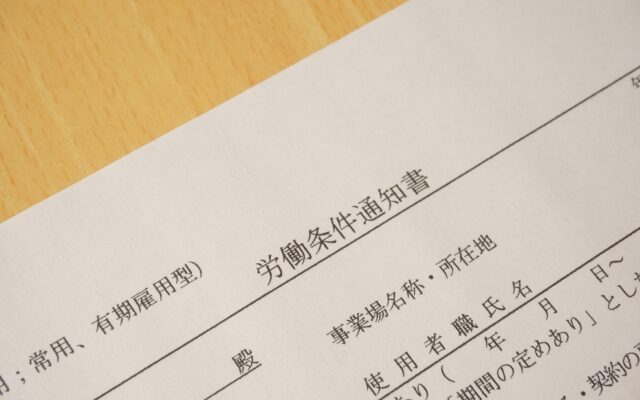
第1054号
「労務関連情報」というテーマで、1時間ほどの
セミナーに講師として登壇しました。
セミナーを通じて、あらためて労務関連、
というか、労務管理について考えてみると、
リスクを回避するという側面をもつ労務
管理ではありますが、
労働トラブルはそれだけでは回避できないと、
あらためて思いました。
——————————————–
労務管理とは
────────

作成にかかわった人材ハンドブック
の利用促進、広報のため、内容を章ごと
に分割して、複数の講師が概要を伝える
こととなり、
社会保険労務士の私が、労務関連について
お話しました。
久々の社会保険労務士の王道のテーマ
で、法改正もあることから、あらため
て労働法の本をはじめ、読み直して考
えてみました。
労働法を知らないと、
確かに、労働基準監督署から是正勧告
を受けたり、個別労働紛争として訴訟
になるケースがあります。
では労務管理とは何か、と言われると
厚生労働省では、
労務管理のポイントとして、
賃金、労働条件、解雇を挙げていますが、
単に、処遇の決定、勤務管理、労働時間
管理、労働契約の終了だけを意識してい
ればよいかというと、
そうではないと思います。
そこから繋がっている、
従業員の募集・採用から配置・人事異動、
教育訓練、人事評価、賃金・処遇、退職
までの
一連の業務に関する管理までが、
労務管理なんだと思います。
これは、労務管理の目的が
労働トラブルの回避ではなく、
秩序の安定と維持を土台として、
その先にある『企業の発展』に
あるからだと思うからです。
労働トラブル回避のためのステップ
────────────────
労務管理は労働トラブルを
回避するために必要だと言われ
ますが、本当に回避できるの
かと言えば、
労働トラブル回避には、3つの
ステップが必要です。
1つめは
企業側の労働法違反がないこと
2つ目は
就業に関するルール・制度が整備
されていること
労務管理としては、ルール・制度が
整備され、かつ、周知されていれば
管理できていると言えるのだと思う
のですが、
根本から労働トラブル回避するため
には
3つ目として、
双方向で批判が言い合える組織、
いわゆる、風通しのよい組織である
こと
ここまでが含まれます。
従業員とのギャップ、行き違いは、
労働トラブル発生の大きな要因
のひとつです。

ギャップはゼロにはなりませんが
小さくすることはできます。
そのために、3つのステップを
“どれも省かずに” 取り組む
ことが大切です。
労働トラブルが発生すると、
対応するための時間や労力、
そして費用がかかります。
ですが、何より
職場環境の悪化はモチベーション
を悪化させ
生産性の低下が収益悪化を招きます。
離職者が増えると、収益が悪化して
処遇が低下する
↓
処遇が低下すると離職者が増える、
という負のスパイラルになります。
なかなか未然に防ぐためにコストを
かけることの決断は難しいもの
ですが、
いずれコストと効果は逆転します。
どんなに法に則って、ルール通りに、
例えば、退職勧奨しても、
人と人は違いますから、
受け取り方が違えば、労働トラブル
に発展するものです。
労働トラブルが起こってから、
ではなくて
それ以前から「対話」ができる
組織の仕組みがあることが重要
です。
今年も法改正が多く施行されます。
高年齢雇用継続給付は給付率が
10%に縮小されたり
教育休暇給付金が創設されたり
育児介護休業法でも
子の年齢に応じた柔軟な働き方を
実現するための措置の拡充がなさ
れます。
これらの制度に対応したルールの
変更だけでも大変ではありますが、
どれもが、
「どういう働き方をしたいのか」
当事者、あるいは未来の当事者との
日頃からの対話の必要性が求められて
いるように思います。
お読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このブログは、メルマガでも平日2回
お届けしています。
ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。