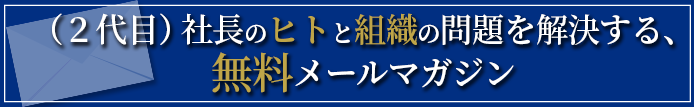第1055号
日米の野球で活躍したイチローが、
米国野球殿堂入りを果たしました。
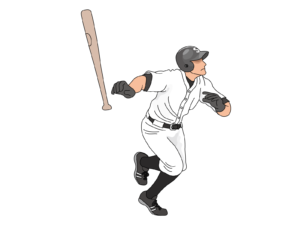
話題になったのが満票での選出では
なかったことです。
満票にこだわるのは日本だけかと
思っていましたが、米国でも話題に
なったようです。
イチロー自身は1票足りなかった
ことを
「(省略)不完全であるというのは いいなって」
と、表現していました。
人の考えはコントロールできません。
自分と違う視点があって当然、
ということを起点としたこの考え方は、
さすがだと思います。
仕事の場では、それを起点としながらも、
合意をとりながら仕事を進めていくこと
が、目標達成につながります。
———————————————–
「これくらいのことは自分たちで
何とかしてほしい」
という言葉を社長から聞くことが
あります。
問題があれば社長が出て行かなく
ても、社員間で解決してほしい
ということです。
実はそういう会社が、
社長の一声で決定したり、ひっくり
返したり
あるいは、
あらかじめ根回ししてから決議する
ような風土だったりすると、
なかなか部下だけで問題解決、と、
言われただけで、できるものでは
ありません。
実際の具体的なやり方はそれぞれの
環境、状況によって違ってきますが、
基本原則は、
何を『目的』にしていて
その実現のために
どんな『目標』を合意すれば
よいのか、
ここをまず、明確にするという
ことが必要です。
明確にするのは誰かと言えば、
社長だったり、上司です。
自分たちで何とかする、
つまり合意形成するには
相手の話を聴きながら
対話を重ねることが
重要です。
ですが、目的と目標が
明確でないと
お互いや自部署の利害が
先にきて、
どうしても話はズレていって
しまいます。
部下の方々が
対話の重要性をわかっていても、
肝心の目的と目標がわかって
いないと、合意には程遠い結果
となってしまいます。
目指すところは自部署の利益
ではなく、会社全体の利益です。

そこに焦点をあてられれば
合意形成の可能性が近づきます。
問題を解決することに集中
しすぎると、自分の意見に
固執しがちなので、
むしろ、得たい効果、状況の
ために何をすればよいのか
という視点に皆が置き替えて
そのために、相手が何を考え
ているのか、
どう感じているか、
これらを察するのではなく
どんどん聞いてみることが
大切です。
自分と違う意見を言う人が
敵ではないことが、徐々に
わかってくるものです。
反論ととらえていたことが
意見、提案として受け取れる
ようになると、
相手が言う言葉がまっすぐ
耳に入ってきます。
目的、目標が明確なうえでの
批判であれば、それもまた
相手を知るということであり、
真のコミュニケーションです。
相手を知ることができれば
信頼が生まれ、
批判になるかもと思って言え
なかった
「それは違うんじゃないの?」と
いうことが言えるようになり、
それが言えるから、
「こういう意見や見方もあるけど、
どう思う?」というように
自分の意見を通すためでなく
いろんな意見が出て、
どういう事をやって行けば目的に
つながるかということに集中して、
全員で多角的な視点から、
考えられるようになります。
そうやって、例えば、
地域で1番の会社になるために
〇〇という製品を作るという
目標に皆が合意して
自分ごとにすることができます。
その次の段階としてお互いの役割
分担が決まっていき
より具体的な行動目標が決まって
目標達成につながっていきます。
お読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このブログは、メルマガでも平日2回
お届けしています。
ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。