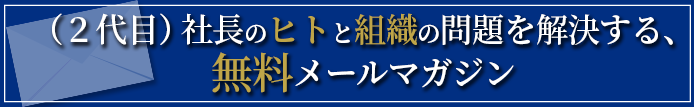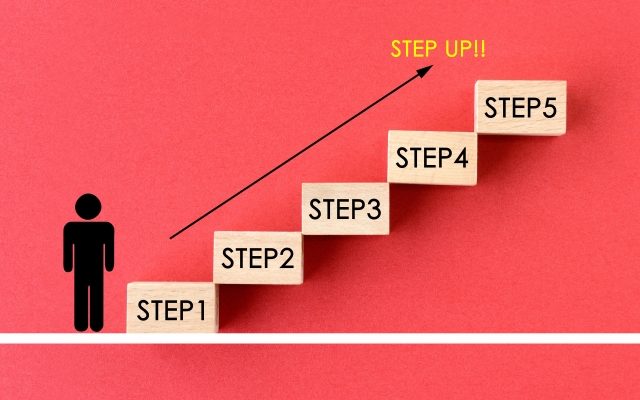
第1064号
損失回避性」を背景とした、人は無意識に変化を嫌う
という『現状維持バイアス』があります。
昇格、昇進した方もおられるかと
思います。
等級が上がって初めて受ける評価では、
よく自己評価と上司評価にギャップが
生まれます。

ここにも「変わりたくない」現状維持バイアス
が関係しています。
——————————————–
評価が高いから等級や職位が上がった
はず。
きっと次の評価も良いだろうと思う方は
多いと思うのですが、
等級が変われば、評価の基準も
変わるので、本人からすると、
下がった、と感じることも多々
あります。
(ジョブ型の場合はまずポストありき
ですから、少し状況は変わります)
いわゆる職能や役割基準の人事制度
を導入しているのであれば、
等級が上がれば、評価がいったん
低くなるのは織り込み済として
設計し、説明している会社もあり
ますが、

要するに、
求められる能力や役割も変わるので
新たな役割要件を満たしていなければ
下がるというわけです。
頭ではわかっているつもりでも、
つい、今までの基準で自己評価して
しまうのも「現状維持バイアス」です。
例えば、
コミュニケーション力が高く評価
されてきて、自身でもそこが強み
だと自信を持っていた社員の方が
自己評価と会社の評価の差に
納得いかないと、部長と人事に詰め
寄ったことがありました。
結論から言えば、制度の説明不足と
言えるのではないかと思います。
人は「変わりたくない」という
無意識の心理があることをたとえ
知らないとしても、
「これからも頼むよ」とか
賃金の話だけしかしていないので
あれば、やはり不十分です。
詰め寄ってきた社員の方のコミュニ
ケーション能力は確かに高いのですが、
昇級したポジションとして上司が望
んでいたのは、他部署との折衝で、
その能力を発揮してほしいということ。
等級制度でも求める役割として
「他部署との連携」という言葉が
入っていました。
そして今期の成果目標である、
プロジェクトを成功に導いてほしい、
というものは、目標ですから達成
しなければならないものとして
取り組む必要があります。
社員の方もこれらのことを聞いて
いなかったわけではないでしょうが、
本人の解釈では、
これまで以上に課の新人を育て、
課をまとめ、プロジェクトの成功に
向けて、成果までには時間が足りな
かったけれど、軌道に乗せた、という
自負がありました。
ただ、それは、今までもやってきた
ことの延長線上であり、
これからは、一段難易度を上げた
ことにチャレンジしてもらわなければ
ならないという上司の考えが伝わって
いませんでした。

他部署との連携に力を発揮し、
かつ、課の目標達成は必須目標だと
いうことが、認識されていない
というギャップ。
”総合的にみれば”、できていると
思ったという解釈。
確かに評価は最終的には
”総合的に”判断することはあり
ますが、
まずは、ひとつひとつ見ていく
ものです。
ここにもギャップがありました。
最終の評価決定のフィードバックまで、
溝を埋めるチャンスはなかったのか
と言えば、
まず、期首の目標設定時点で、
自分の役割とやるべきことが
明確に認識されていなかった
ことが、最初の掛け違いでした。
評価項目について、文字を読んで
説明するだけでは足りません。
自分の言葉で、どう理解したかを
本人に確認することも大切です。
評価期間6カ月の間に、
月1回程度、面談を行う意味は、
進捗の確認や
何か課題はないか、等を確認し、
ギャップがあれば、埋めて軌道修正。
やり方がわからなければ一緒に考える
ことです。
この意図を理解できていれば、
評価決定後に詰め寄られることは
回避できました。
この社員の成長する大事な機会を
無駄にしてしまいました。
経営に経営目標があるように
人材にも人材目標があります。
毎年ベースアップが求められ
賃金と評価の関係性がぼやけて
しまう今だからこそ、
会社の規模関係なく
等級制度(キャリアパス)は、
作って、
「どのように育ってほしいのか」
伝える仕組みとして、活用したいもの
だと思います。
お読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このブログは、メルマガでも平日2回
お届けしています。
ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。