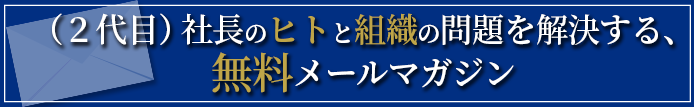第1062号
人の話を聞いている途中で、
「あぁ、そういうことね」という
瞬間があります。
部下の報告や相談に耳を傾け
ながらも、どこかで、
「あっ、わかった」と思って
しまうと、

そこからは、自分の答えを持って
話を聞いてしまうので、
コミュニケーションエラーが起こ
ります。
このエラーを回避するにはいったん
自分の答えを保留するしかありません。
————————————————-
わかったつもりの危ないところは、
本人からすれば「わかっている」
から、もっとわかる必要がないこと
です。
そうなると、相手のその先の話は、
聞いているふうに見えても聞いて
いない、
ということが起こってしまいます。
予告編だけ見て、犯人がわかった
つもりで映画を観に行くと、実は
真犯人は違っていた、というよう
なことが起こり得ます。
「わかっていない」ときは、
わかろうとして、わからない部分を
聞こうとしにいきますが、
本人としては、もう”わかった”と
思っている場合
わからない部分は見当たらないので
わかろうとしにいく必要がありません。
後になって、ようやく気が付いて
「なんでもっと早く言わないんだ」
「いえ、伝えています」
という行き違いが起こります。
これを防ぐには、
いったん、自分の答えを保留する
ことが大切です。
先日
「AI×人材育成をテーマにした講演会」
に参加しました。

登壇された昭和女子大学ダイバーシティ
推進機構キャリアカレッジ学院長でも
ある熊平美香さんは、
人と人の違いを
「人は同じ事実を拾わない」という
表現をしていました。
だからこそ、自分の経験や感情、
価値観によって形成された
「ものの見方」を
いったん保留にすることで、
自分を客観視できるようになって
傾聴を続けることができます。
そして、その対話のなかで、相手の
経験、感情を聞き取ることで、
自分とは同じではない価値観を
理解することができるようになり
ます。
ものの見方を保留することができないと
AIが当たり前の時代には、真の意味での
AI活用ができないのではないか、と思って
います。
AIの活用の仕方のセミナーが多く開催
されていますが、
上手く活用するためには、こちらが
どういう「問い」をたてるかによって
より優れた回答が得られる、と言われて
います。
質問力とでもいうのが問われるわけですが、
その先に見えてくるのは、AIが限りなく
人の思考に近づいてくる、ということ
なんだと思います。
無意識に、質問にはその人の「ものの
見方」が反映されているからです。
だとすれば、このAIの答えについても
いったん、評価判断を保留する必要が
あります。
AIもまた、「限定合理性」であり
「完全合理性」ではないということに
なります。
答えを出せる既知の問題であればAIは
過去の事実から有効な答えを導きだして
くれるかもしれませんが、
答えがない未知の問題については
(今のところ)人間の頭を使うしか
ありません。

奇しくも、先日最終回を迎えた
TBS日曜劇場「御上先生」が一貫して
言い続けていたのが「考える力」
考えても答えの出ない問題について
投げ出さずに考え続ける力です。
笑えない未来として
AIが1on1面談を代行する時代が
来て、そこから被面談者のAIへの
信頼感が生まれようとも、
人が、考える力を手放さない限りは、
人と人の信頼関係は揺るがない
のだという希望が持てます。
そのためにも、
わかったつもりの落とし穴に
落ちないことが大切です。
お読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このブログは、メルマガでも平日2回
お届けしています。
ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。